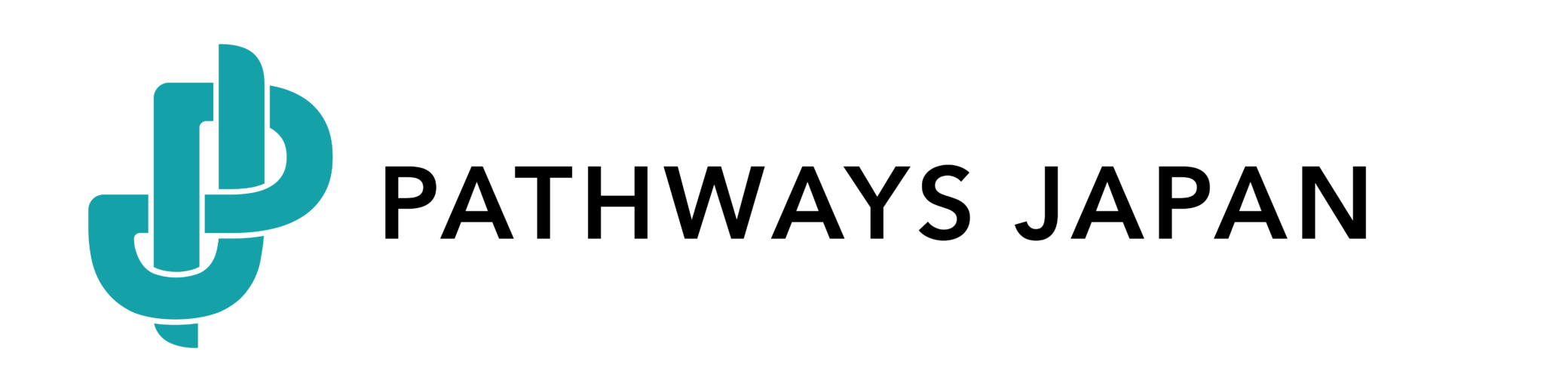はじめて日本に降り立って見た風景は今でも鮮明に覚えている。羽田空港から都内に向かう車窓から見えた夕暮れ時の東京タワー。しばらくして目の前に現れた、新宿か銀座か当時は見当もつかなかったが、東京の夜の街を彩るネオンサイン。
トルコの在留カードの期限は残り1ヶ月あった。更新することもできたが、気がついたらカードを拳でぎゅっと握りしめていた。トルコに戻る選択肢を残したくなかった。自分の判断に迷いたくなかった。これから、ここ日本で、自分の人生を自分で切り拓いていくのだと、決意を新たにした。
12歳で難民として故郷を追われたアブダッラは、自らの意志で日本に活路を見出すことを選び、19歳で単身来日した。それから4年。彼は日本で何を経験し、何を思い、どんな将来を見据えているのだろうか。

アブダッラの故郷はシリアのホムスだ。シリア西部にある都市で、首都ダマスカスとアレッポに並ぶシリア第3の大都市として知られている。アブダッラに聞くと、ホムスの人たちは「ユーモア好き」が多いという。物腰が柔らかで、相手の心を和ませつつ、その機微を読むことに長けていそうな彼からもそんなホムスの気質を感じる。
2011年3月、チュニジアに端を発した「アラブの春」と呼ばれる民主化の動きがシリアにも波及した。改革を求める市民たちの平和的な抗議デモは、政府による激しい弾圧や周辺諸国の干渉を受け、やがて政府軍と反体制派の戦闘へと激化していく。ホムスは、その紛争で両者による激しい戦闘が行われた場所の一つだ。旧市街では、戦禍に巻き込まれ避難ができず、食糧や医療品などの支援物資の輸送も行われないまま、多くの市民が取り残され、死に追いやられた。
2018年以降、政府軍による大規模な奪還作戦後に国土の大半が政府の掌握地域となったが、社会経済の不安定な状況は続いている。長期にわたる戦闘で国内は荒廃し、未だ回復できていない。紛争が勃発した2011年からの10年間で、30万人*を上回る民間人が亡くなったという。
| イエメン、サウジアラビア、トルコを経て辿り着いた日本
紛争がはじまりまもなく、アブダッラ一家の身にも戦火が迫る状況となり、まずは、国内の別の町に避難した。その後、シリア国内に留まり続けることが難しくなり、近隣国のイエメンに移った。しかし、イエメンでもアラブの春の余波で内戦が始まり、サウジアラビアに再び避難。家族は両親、姉2人、兄1人 弟1人の7人。一家は、生き延びるために何度も移動を余儀なくされた。
ひとときの平穏な生活を取り戻したサウジアラビアで、アブダッラは高校を卒業した。その頃には、昔から好きだった情報技術を学ぶために、IT先進国である日本に行きたいという思いが強くなっていった。日本のアニメや漫画も好きだった。お気に入りは「進撃の巨人」。アラビア語翻訳のアニメ作品を通じて、日本への憧れは膨らんでいった。
しかし、日本行きのビザを得ることは容易ではない。アブダッラは、日本に暮らす従兄弟の力も借り、「留学生」として来日する道をインターネットで探したところ、偶然、日本語学習2年間学費無償のプログラム(当時は難民支援協会の事業)に辿りついた。次の応募は半年以上先だったため、トルコに移動し、トルコの大学で勉強をしながら、応募書類を整えた。トルコのイスタンブールで行われた応募面談で話した面接官は、はじめて話した日本人だった。最初は緊張したが、自分が日本で学ぶことを本気で考えていることや意気込みを無心で伝えたという。そして、無事、合格の通知を受けた。
日本行きについて、両親はとても心配したという。特に母親は反対だった。「アルバイトをしながら勉強することが、僕にできるのか、不安だったみたいです。トルコへ単身渡った時も心配していましたが、トルコと比べたら、比較にならないくらい日本は遠いです。お母さんは日本のことをほとんど知りません。お母さんが思う日本のイメージは『ロボットがどこにでもある国。ウーバーイーツの宅配もロボット』でしたから」と、アブダッラは笑いながら振り返る。文化も宗教も馴染みがないうえに、あまりにも縁遠いアジアの国で息子が生きていくことを想像するのは、母には難しかった。
両親の不安は受け止めつつも、アブダッラの気持ちは揺るがなかった。早く自立したい、自分の力で生きていきたい。親元を離れたいという若者らしい気持ちと、このままとどまっていては自分の未来は切り拓けないという焦りもあったのだろう。最後には、両親は彼の選択した道を応援してくれた。
両親には「日本で何かあったらトルコに帰るから」と言って、納得してもらったらしい。もちろん、彼にはそのつもりは微塵もなかった。

| 絶望に見えても希望はある、と今は思える
現在は、北関東にある大学で情報電子工学を学んでいる。この春で3年生になった。1年目は授業に物足りなさを感じていたが、2年目から少しづつ専門的な内容が増えてきて、面白くなってきたという。
来日後の2年間は、日本語学校に通い、パン工場でアルバイトをしながら、ゼロから日本語を学んだ。大学受験は、日本人と同じように日本語で行われる、数学、理科、日本語の日本留学試験(EJU)を受け、見事好成績を収め、2年間で日本語で学ぶ学部への進学を果たした。奨学金も取得した。現在は、マクドナルド、アパレルのGU、大学でのティーチングアシスタントのアルバイトを掛け持ちしながら、勉強に励む。授業はすべて日本語で行われる。日々忙しそうだが、充実している様子が話している姿からも伺える。
ここに至るまでにも辛いこともたくさんあった。日本語学校2年目には、新型コロナウイルスの感染拡大でさまざまなことが制限され始めた。大学入試に必要な日本語能力試験(JLPT)や、日本留学試験(EJU)の試験準備が間に合うか心配だったが、幸い、2ヶ月後には、対面での授業が再開された。
9時から12時半まで日本語学校、その後、17時まで学校に残り、大学入試に必要な数学や物理を独学で取り組んだ。18時から23時まではパン工場でアルバイト。2年間働いた工場では、パンの材料を混ぜる、成形する、包装するなどすべての工程を経験した。工場内は蒸し暑く、体力的にも仕事は辛かった。
日本人の友人を作ることも簡単ではなかった。大学2年目までは、留学生と一緒にいることが多かった。台湾、マレーシア、インドネシア、中国など、さまざまな国出身の友人がいたが、2年目が終わり、留学生仲間は、皆帰国してしまった。そして、彼は1人残された。
「自分には日本人の友達がいない、日本人の考え方や価値観、日本社会のことがまったくわかってないってはじめて気づきました。このままじゃいけないって思って、そこから、自分の行動を変えていったんです」
そして、積極的に自分から声をかけていき、少しづつ日本の友達ができるようになったという。
同世代の日本人学生の中には、勉強に前向きでなかったり、将来への希望が特にないままに過ごしている人も少なくないと、アブダッラは観察する。時には、「シリア人」ということで、嫌な経験をすることもある。だが、彼は「日本人もシリア人も、人それぞれ。ネガティブなこと言う人とは離れるようにしている。嫌なことがあっても、気にしないようにしている」と冷静に受け止める。
自分の生い立ちについては、「聞いてくれたら話したい」という。自分が伝えなかったら、シリアで起こったことは忘れられてしまうという焦りもある。
「戦争は怖いものです。でも、絶望に見えても希望がある、と今は思えるんです。今では、どんな状況でも乗り越えられるという自信もつきました。日本に来て4年。最初は苦労しましたが、やっと、ここに根を張り、精神的にも安心して暮らせるようになってきました。そういう自分の経験を伝えたいです」
| 経験から見出した自分の生き方
自分の行動を変えることで、人生は変えられる。日本での毎日の積み重ねから、そんな思いに至った。日本語学校で学びながら、独学で大学入試の勉強をし、パン工場で働く日々は、楽ではなかった。当時を振り返り、「どう乗り越えたのか、想像ができない」と朗らかに笑う。工場のバイト仲間は若い外国人が多かったが、過酷な労働環境に、お互い愚痴り合い、ストレスを発散するような同僚も少なくなかった。
「ネガティブになるのは簡単。でも、チャンスは自分から捕まえないと逃げていく。物事をポジティブに考えれば見方は変わる。それしかないと思いました」
そして、彼は改めて「自分が選んだ判断の責任は自分で取る」ことを強く意識した。「今、頑張って貯金をすれば、大学で勉強する道が拓ける」、「今日稼いだお金から千円は自分へのご褒美にしよう」と、自分を鼓舞しながら。
そんなアブダッラの気持ちを後押ししたのは、毎日、自転車に乗りながら見るありふれた平穏な風景だ。
「工場とアパートを自転車で行き来するとき、川沿いを通るんです。普通の風景なんですけど、平和で、夜も歩けるし。毎日眺めていて、やっぱりここに住みたいなと思ったんです」と、数年前の自分を思い出す。

| ぽっかりと穴が空いたシリアでの記憶
12歳で故郷を追われ、難民となり、自分の力が及ばない事情に翻弄されたアブダッラ。だが、彼は、人生を取り戻すことを諦めなかった。来日して4年間。23歳の彼は、着実に自分の人生を自分で切り拓いている。
シリアに戻ることは、今は考えていないという。「日本が第一のホームかな。そうなったらいいな」と、はにかみながら話す。今の在留資格は、来日時と同じ「留学」だ。卒業後は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など就労に関する在留資格に切り替えることを見据え、すでに日本語能力試験の最も難しいレベルであるN1を取得した。
「シリアでの思い出は、ぽっかりと穴が空いたようになくなってるんです。小学校の思い出は、夢みたいに消えてしまいました。学校に行ったり、ホムスで普通に過ごしていたあの平和だった世界は自分の中には存在していません。当時の友人は1人だけ繋がっているけど、それ以外はどうなっているか。亡くなった友人もいます」と淡々と話す。
10代前半の幼いアブダッラが受け止めるにはあまりにも過酷な現実だったのだろう。心の傷は簡単には癒えない。だが「難民となる経験をしたことで、自分は成長できたのだ」と過去の自分を受け止める。
| 平和な時間を責任を持って生きる
社会で「成功」したいという思いが強い。ただ、アブダッラの思う「成功」は、私たちの多くが考えるそれとは違う。
「経済的に自立することはもちろん大切だけど、僕の思う成功はそうじゃないんです。自分の力を生かして、社会でチャレンジできるのは、社会が平和だから。世界には平和な生活が『夢』である人もいるんです。平和な時間は貴重なもの。だから、その時間を大切に生きたいし、そう生きることは、平和な社会で生まれた者の責任だとも感じています」
私たちの日常が今ここで存在する前提としてある「平和」。だが、アブダッラの指摘は、日本は本当に「平和」なのかと改めて問うているようにも聞こえる。
難民受け入れは、社会の鏡だと言われる。難民を受け入れる側の課題も価値も映し出す鏡だ。異なる他者に寛容か、排他的か。多様性を認めるのか、同化を強いるのか。日本社会の「平和」は誰かの犠牲の上に成り立っていないか。難民受け入れを通じて見えてくる社会の複雑さに向き合い、よりよい社会の実現を目指して取り組みつつ、難民となった若者に新たな道筋を提供する機会を増やしていきたい。
注釈
* 国連人権高等弁務官, プレスリリース, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-human-rights-office-estimates-more-306000-civilians-were-killed-over-10(2022-4-8)
取材・文/田中 志穂